日々精進!9月活動報告!果たして公園での手持ち花火の実証実験は成功したのか!
2025/09/17こんにちは。永渕ふみたかです。皆様いかがお過ごしでしょうか?
8月定例会は、8月25日に開会し、9月16日に閉会しました。
今回のブログでは8月定例会での一般質問の内容を振り返ります。

佐賀市内で花火はやっても良いのか?の質問後の実証実験を振り返ります
8月定例会一般質問を振り返る!!
Q 市は手持ち花火の社会実験を2年おこなっているがどのくらいの市民の方が実証実験に参加されたのか
A 令和6年度は、巨勢公園と多布施川河畔公園で6日間、市役所前公園で1日実施し、合計113組500人、令和7年度は、巨勢公園、高木瀬ふれあい公園で、4日間、市役所前公園で3日間実施をし、合計137組594人が参加した
Q今回の結果を市としてどのように解釈されているのか
A 実施にあたり大きな問題はなく、市民の間で公園での花火に対するニーズが高いと認識
Q 実証実験を終えて今後の当市の対応について問う。
A 来年度以降はさらに踏み込んだ社会実験を行い、その結果をもとに制度やルールを検討していきたい
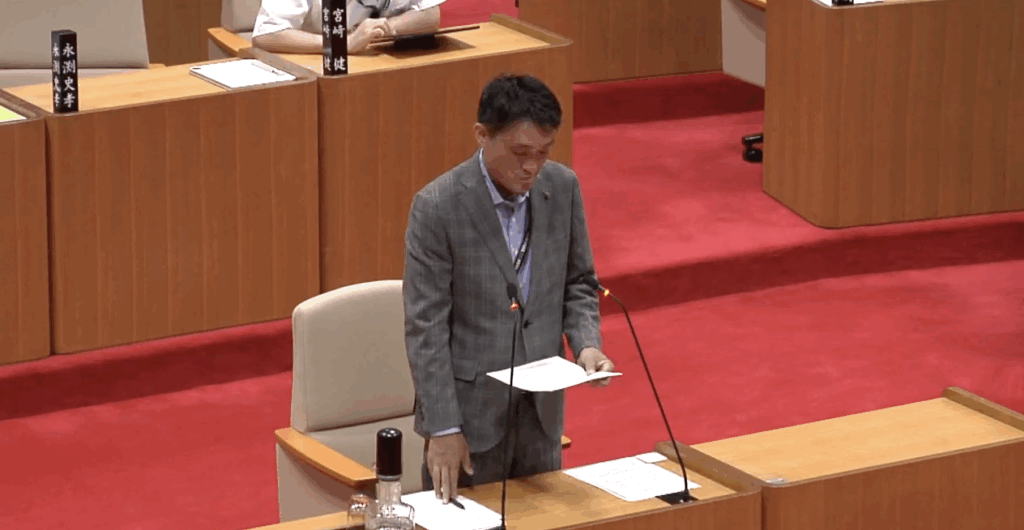
質問をする私
 答弁をする都市戦答弁する一丸 都市戦略部長
答弁をする都市戦答弁する一丸 都市戦略部長
■解説
令和5年8月定例会で花火を市民はどこでやれるのか?という質問をしました。その後、昨年度と今年度と二年間実証実験が開催されておりました。総括では、どのくらいの市民の方が実証実験に参加されたのか?その実績の確認の質問をいたしました。令和6年度は、巨勢公園と多布施川河畔公園で6日間、市役所前公園で1日実施し、合計113組500人、令和7年度は、巨勢公園、高木瀬ふれあい公園で、4日間、市役所前公園で3日間実施をし、合計137組594人が参加がありました。特に今年度は、昨年度より日数を減らしたにも関わらず、また今年度は、広報PRもそこまでなかったと記憶していますが、良い結果であったと思っています。当市の解釈での答弁においても、良い事業になったと感じているようでした。当市の手持ち花火実証実験開催の決断というのは、市民の皆様の貴重の思い出の1日を演出したのではないのかと思っています。。家族、親族が集まるお盆休みのときに、その夜に楽しみがあるというのは、都会から来た子どもたちなどにとっても、佐賀市を印象づける効果的な一面があると私は思います。今後、実験を超えて、夏は公園で、手持ち花火をする家族が増える当市の風物詩になることを期待いたします。
今回の一般質問の動画
日々精進!秋は勝負の時期、 引き続き活動を頑張ります。
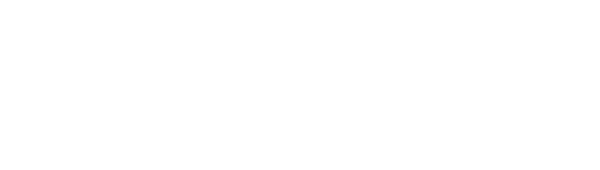






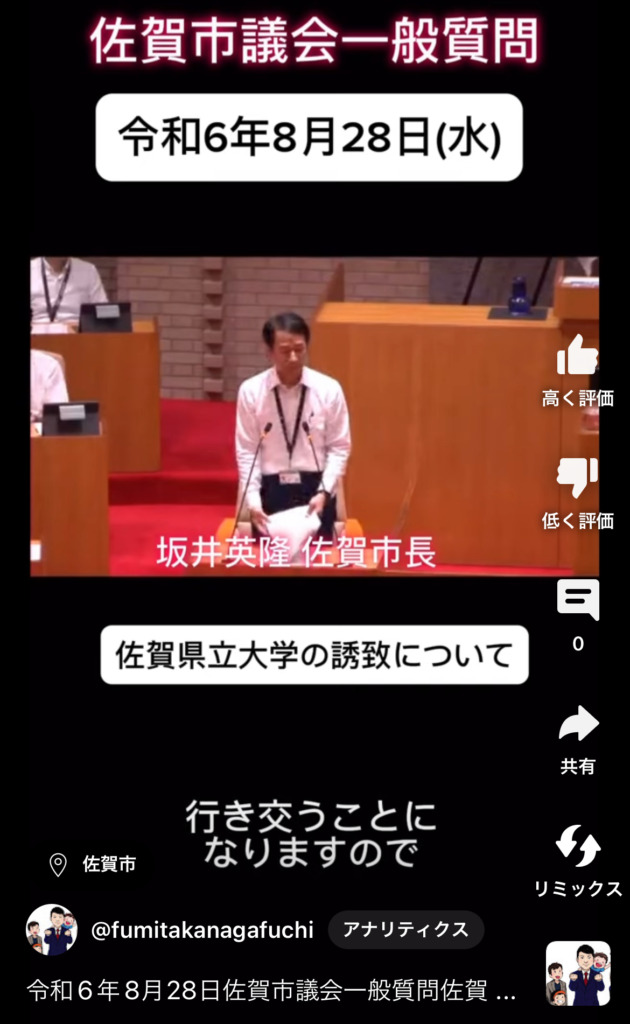

 答弁をする都市戦略部長
答弁をする都市戦略部長





